目に見えるものより、見えないつながりをデザインする。
櫻井 亮 Ryo Sakurai

東京情報デザイン専門職大学 准教授
楽しみながら人や社会と共生し、
高め合っていく存在へ。
変化が激しく、先が見えないこの時代。これからの学生が目指すべきエンジニア像とは?
ともに日本のモノづくりの黄金期を支え、新しい教育のあり方を切り拓いてきた二人が、
今を生きる学生たちの未来について語り合う。
中鉢:奥山先生にデザインしていただいたこの校舎ですが、初めて完成を目の当たりにした時から非常にポジティブなサプライズがありました。まず、採光が素晴らしいですね。ガラス面が広くて、外構の緑に包まれている感覚があります。非常にオープンで、同時に洗練も感じます。美術館のような洒落た雰囲気ですね。
奥山:ありがとうございます。やはり江戸川区初の4年制大学として地域の期待も高まっていたので、地元の方にも親しみやすい開放的な空間を目指しました。同時に「専門職大学」というアイデアを反映できるよう、専門的な教育研究機関らしいテクノロジー感の表現にもこだわりました。親しみやすさと先進性、異なる二つのコンセプトを共存させるべく、二つの校舎を「緑の棟」「ハイテク棟」と二軸の方向性でデザイン、ブリッジで一つにつないでいます。一方には地域に開かれたカフェなどを設け、もう一方には第一線の研究者が最先端の実験に取り組める環境を整えられたら、と考えています。

中鉢:先日、学生たちがキャンパスに何を求めているかを知る機会があったのですが、少し予想外の意見がありました。集まってワイワイガヤガヤと過ごせるスペースと同時に、一人になって静かに思索を深められるスペースも欲しいと言うのです。 企業でもそうですが、今はどの業界でも業務内容や働き方が目まぐるしく変化しています。それに伴って人とのコミュニケーションのとり方やストレスの生まれ方も大きく変わっていくので、建築に対するニーズも日々変わっていくのでしょうね。
奥山:そうやって実際に日々使ってくださる皆さんから実用に即した提案をいただけると、常に時代のニーズにマッチしたキャンパスを一緒につくっていくことができますね。今は建築だけでなくありとあらゆる分野で変革のスピードが加速しています。それは言い方を変えると「先がまったく見えない」ということでもあるのですが、だとすればモノづくりの考え方にも、その手前にある教育のあり方にも、これまでのような目に見える答えはないのです。これを学べばこういう仕事に就けるというセオリーもありません。何か一つに焦点を定めて、集中的に取り組むことも大事なことですが、今から興味の幅を一点に絞って、そこだけに目を向けていても、就職する頃にはその業界自体がなくなっている可能性もあります。では、今の学生は何を学べばいいのでしょう。ちょうど今、より良いキャンパスづくりの提案をいただいたように、いろいろな意見を持ち寄ってみんなで一緒につくり上げていく。その中に答えがあるのではないかと私は感じています。
中鉢:世の中がどう変わっていくかは誰にもわかりませんが、確実に一つだけ言えるのは、どういう時代であっても人や社会と共生できる力が必要だということです。その共生こそが情報デザインの本質、いわゆる「ワイガヤ」なんですよ。昔は全部一人で考えました。でも今ではあらゆるモノ、あらゆるサービスが多元化・複合化して、もう一人では手に負えません。ある側面では文系の感性が必要だし、別の側面では理系の知識が不可欠になる。そういった多種多様な知見を集めて整理していくプロセスが情報デザインなのです。
奥山先生は自動車のプロダクトデザインを数多く手がけていらっしゃいますが、まずこれは何のためにつくるのかというコンセプトを立てる、それを形にするための構想を練る、設計をしてレンダリングを行う、プロトタイプをつくって試作を繰り返す、といった一連の流れをデザインしなくてはなりません。一人ひとりが自分の担当業務だけを分業的に受け持てばいい、というのではないのです。先ほど奥山先生がおっしゃったように、明日にはその業務はなくなっているかも知れないのですから。だからみんなで意見を出し合って、全体を最適化するために各過程をどうすべきかを話し合う。そうして周囲と共生しながら統合力を発揮できる人材「情報デザインエンジニア」がこれからますます必要とされていくでしょう。

奥山: 自動車を所有する人が年々減っている中で、なぜ私が今も好きでつくり続けているのかというと、自動車にはあらゆる分野の知識と技術が統合されているからです。エンジンという内燃機関を中心に、機械、電気、材料と工学的な側面だけでも数多く、家具や建築の要素もあり、今では情報通信の技術も不可欠です。その中の一つの側面を深掘りしていくと、他の面とつながって視界が開ける。そうして広がり続けるから、どこまでも興味が尽きないのです。「T型人材」という言葉がありますが、これは1点を深く掘り進めることで、横にも知見を広げていける人を表します。とにかく興味のあることなら何でもいいから突き詰めてみる。すると、その分野に関してははっきりと自分の考えを持ち、人に伝えられるようになっていきます。そうして深く掘り下げて得た知識や教養には、他の分野と関連する部分や相通じる側面があるものです。その視点から、馴染みのないテーマに対しても立体的に考察でき、人と意見を交換し、高め合っていくことができるようになります。先ほど学生たちがキャンパスに求めるものとして、「仲間と集える空間」と「一人で考える空間」を挙げていただきましたが、学生たちは無意識に共生と集中の必要性を感じていたのかも知れませんね。
中鉢:一人で考察を突き詰める、それを誰かと共有する。そのために必要な教養とは何でしょう。数学でしょうか、情報学でしょうか。私は何よりも、国語力が重要だと考えています。情報デザインに国語は関係ないと思う学生もいるでしょうが、それは大きな間違いです。言葉と言葉のつながり方、その流れをうまく整理して文脈を組み立てていくことは、プログラミングにも通じることです。さらにそれをつなぎ合わせて一つの商品やサービスをつくり出していく、そのゴールに向かって仲間と知識や意見を伝え合う。あらゆる場面で言葉のコミュニケーション力が必要とされるのです。
奥山:デザインの中には「絵のデザイン」と「言葉のデザイン」があると考えているのですが、絵のデザインだけでいうと、ツール進化によって、すでに誰でもできるものになっています。小学生でも3Dのモデリングができる時代ですから。そこに違いをもたらすのは何かというと、的を射たコンセプト立てや魅力的なストーリーづくり。つまり、言葉のデザインなのです。学生の皆さんには、その重要性に早く気づいてほしいですね。
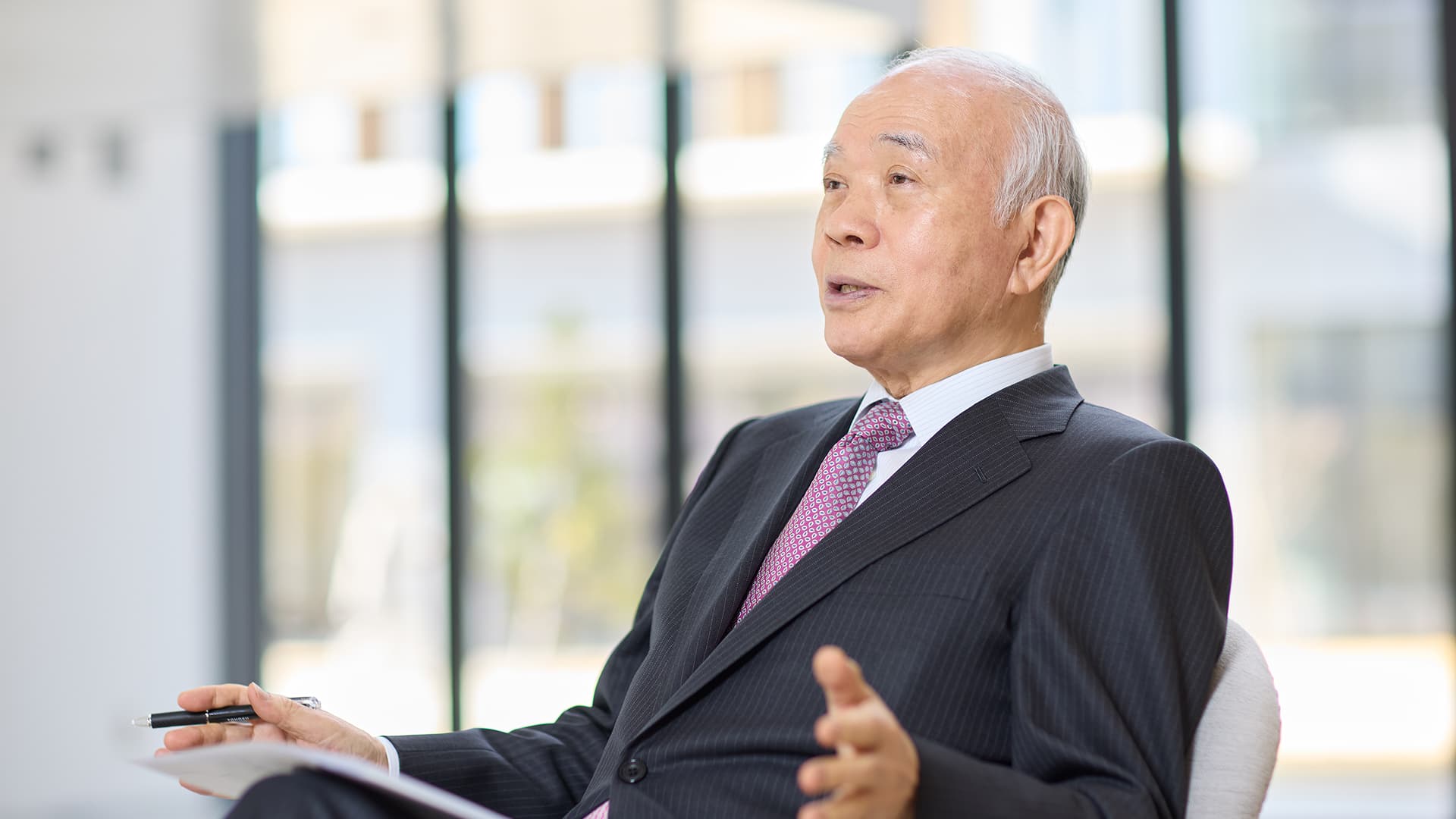
奥山:空飛ぶ車をつくりたい、新しい街づくりをしたい、スマートフォンの中のアプリづくりもやってみたい。そのために今のうちから学んでおくべきことというのは、正直、何だっていいのです。先のことは誰にもわからない、答えは誰も持っていないのですから。すべて自分で決めればいい、決めていくしかないのです。学生として学びながら、社会人として働きながら、好きなものも考え方も次々と移り変わっていくでしょう。どんどん変わっていけばいいと思います。今、自分がやりたいことにどこまでも夢中になる。理系も文系も関係ありません。そこに垣根はないのです。その時その時、自分が心から楽しんでいるという実感が、長く成長を続けるために重要なことではないでしょうか。
中鉢:実は、私も元は文系で、物書きを目指していたんですよ。
奥山:そうなんですか。意外ですけど、少し納得行く部分もあります。そもそもデザインというのは理系と文系の中間なんですよね。どちらにも首を突っ込んで、全体を好きな方向へ動かしていける、言わば「いいとこどり」ですね。
中鉢:まさにその通りですね。そういった既存の枠に捉われず、自由に発想し、柔軟に行動できる人材を育てていくことが、本学の使命だと考えています。