目に見えるものより、見えないつながりをデザインする。
櫻井 亮 Ryo Sakurai

東京情報デザイン専門職大学 准教授
この国の未来を担う情報分野で、
生き抜く力を身につけよう。
資源も土地もない、人口も減り続ける国に未来はあるか?
これからの世界を生き抜くヒントを探すため、
ゲーム業界の最前線を進んできた大舘先生と本学 1 年生が語り合う。
学生:大舘先生の専門分野について教えてください。その分野を TID で学ぶことにはどのような意義がありますか。
大舘:私の専門分野はデジタルエンターテインメントで、中心的に取り組んでいるのはゲームの制作ですね。ゲームの制作演習・制作実習をメインとしています。私のキャリアの大きな部分をコンピュータグラフィックスが占めていることもあり、その流れで CG 関連にも携わらせてもらっています。それらを TID で学ぶ意義ですが、まず「東京情報デザイン専門職大学」の「デザイン」の部分に何をイメージしますか。グラフィカルなものやビジュアル的なものを連想しますよね。しかし、英語の辞書で”Design” とひくと、「図案を描く」の他にも「企画・設計する」といった意味が出てきます。情報デザインの「デザイン」は後者です。たとえばコンピュータグラフィックスで言えば、素敵なキャラクターを作ることより、それを描き出すためのツールや仕組みを作り出す。それが、TID の学びです。表層的な見え方だけでなく、内面的な構造や成り立ちまで理解する。そのための観察眼や洞察力は、企画・設計の視点で情報技術を学ぶ TID だから⾝につけられるものだと言えるでしょう。

学生:今回私たちが参加した企業プロジェクトにも、TID ならではの学びが反映されているのでしょうか。
大舘:その通りです。本学が推進している企業プロジェクトでは、TID がただの「大学」でなく「専門職大学」であることの意義に触れられるはずです。専門職大学というのは、職業人としてすぐに戦力となる人材を育成する場所です。しかし現代の日本において、企業文化と学生文化の間にある隔たりは非常に大きい。その隔たりを学生のうちに少しでも埋めておこうというのが企業プロジェクトの狙いです。企業が掲げる専門的な課題に学生が向き合い、解決策を発表・提案する。学生は社会に実在する現場のニーズに触れることができ、企業にとっては業界の常識に縛られない学生の自由な発想と出会うことができます。学生のお二人に取り組んでもらったのはバンダイナムコスタジオの課題でしたね。本件に関しては、私がクリエイター・プロデューサーとして長年在籍した企業でもあ ったので、課題設定から進捗確認といったプロセスの設計まで携わりました。企業から課題が提示されてからは後方からの支援に回り、必要に応じて学生に助言を行なう役割を担いました。今回の企業プロジェクトは、アワードを受賞したゲームのアクセシビリティ(利用のしやすさ)を調査するという内容でしたが、お二人は参加してみてどうでしたか。

学生:まず実際にゲームをプレイしてみて、視覚障害対応がなされているポイントを見つけ出し、ネット上のレビューと照らし合わせてレポ ートにまとめていく流れでした。最初は誰がいつまでにどこまでやるか、というチーム内での役割分担に手こずることもありましたが、最終的には何とかまとめ上げて、優秀チームに選ばれることができました。
大舘:皆さんは入学してまだ間もない時で、お互いにどういう連絡手段があるのかも定かでない状態からのスタートでしたので、連携を取りにくい部分もあったと思います。しかし、社会に出たら初対面の相手とすぐに効率的な連携をとれるよう環境を整えなければいけません。誰かではなく自分がやるのです。その重要性に気づく良いきっかけになったのではないでしょうか。
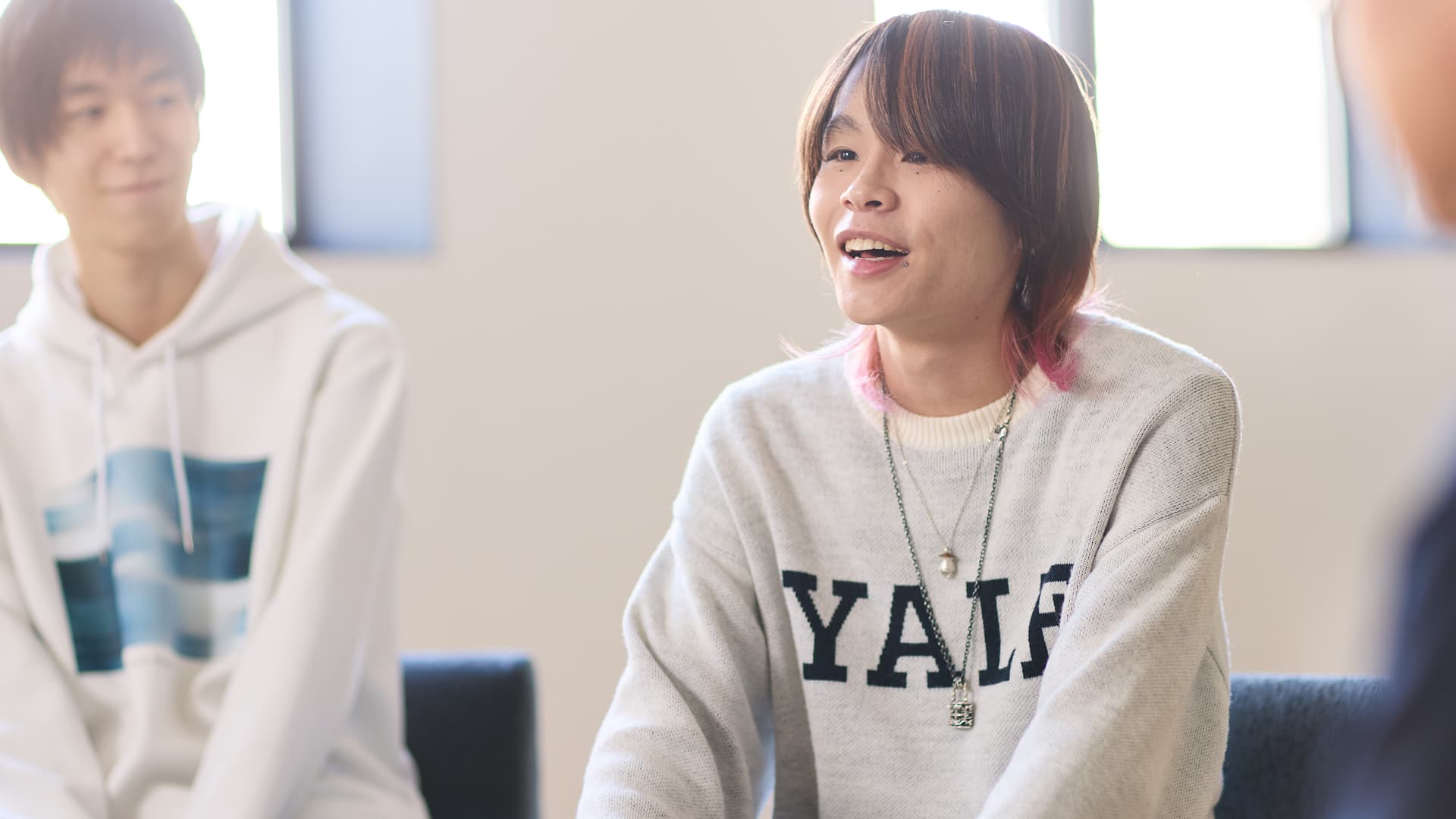
学生:私も同じチームで参加したのですが、高校時代からグループワークの経験があり、少しノウハウもあったのでうまくまとめられると思 っていました。しかし、高校までと違い、大学では一人ひとり日程が異なり、出される課題の量も、授業後の生活パターンもすべてバラバラです。ミーティングの調整一つでこんなに大変なんだと痛感しました。
大舘:それも、社会に出るとみんな思い知らされることですね。職種も年齢も立場も異なる人たちが、別の業務を山のように抱えている中で集まらなければならない、という場面は多々あります。今回、最初は白紙の状態から取り組んでもらい、中間レポートの段階でゴールイメージを明確に打ち出し、意思統一を図りましたよね。それをきっかけに同じ方向に向けて連携をとれるようになりました。あの感覚を覚えておいてください。みんなで目標を共有し、そこへ向かうのに必要なものは何かを話し合う。そのプロセスを重ねていけば、うまくいかないことがあっても、いつでも軌道修正できますから。ところで学生の眼には、どういったところがTID ならではの学びとして映るのですか。
学生:私の一番の推しは、学修サポートがある点ですね。高校までの授業でわからないままやり過ごしてしまったところが多々あるのですが、そういった見直しにも付き合ってくださっています。TID の先生方は距離が近くて相談しやすいですし、私が何に躓いているのか自分では気づけない点もすぐに察して私に適したアプローチを考えてくださいます。中高時代はあんなに数学ができなかったのに、微分や積分に興味を持ち始めている自分に驚かされます。
大舘:そういってもらえると、大学としても嬉しい限りですね。若者が学びに関心を持つことは、日本の未来のためにも重要なことです。この国には資源がありません、⼟地もありません、人口は減っていくばかりです。その中で世界と渡り合うには、学びを通じて一人ひとりが知識と技術を磨いていくしかありません。学びの力を、限られたスペースで、わずかな物資で、少人数でも大きな価値を生み出せる情報産業に活かしていく。その分野で生き抜くための学びが、ここには揃っています。