誰もが、何にでもなれる可能性を持ってる。
村上 博 Hiroshi Murakami

東京情報デザイン専門職大学 准教授
目に見えるものより、
見えないつながりをデザインする。
大きすぎて掴みきれない「情報デザイン」という概念。
何を学べばその本質にたどり着けるのか?
学生に、社会人に、広くその価値を伝えてきた櫻井先生が本学 1 年生に語る。
学生:私たちはここで毎日「情報デザイン」を学んでいるのですが、その「情報デザイン」とは何なのでしょう。櫻井先生の定義を聞かせてください。
櫻井:情報デザインには主に情報とデザインの2つの領域あるんですが、そのデザインの方を担当しています。 ただ私自⾝はデザイナーでもないですし、美大で扱うようなデザイン、たとえばパッケージデザインとか、衣装デザインとか、そういうものではなありません。より広い視点で、サービスをどう捉えるか、体系をどう捉えるか、ビジネスをどう捉えるかという意味でのデザインを非常に重視しています。それが情報とつながった時にどうなるかということも全般的にお話をしています。大学以外にも起業家教育やスタートアップなどの活動も行っていますので、そちらではどうやってビジネスをつくるかといった提案が多くなりますが、この学校ではどちらかと言えばデザイン思考という考え方を中心にお伝えしています。
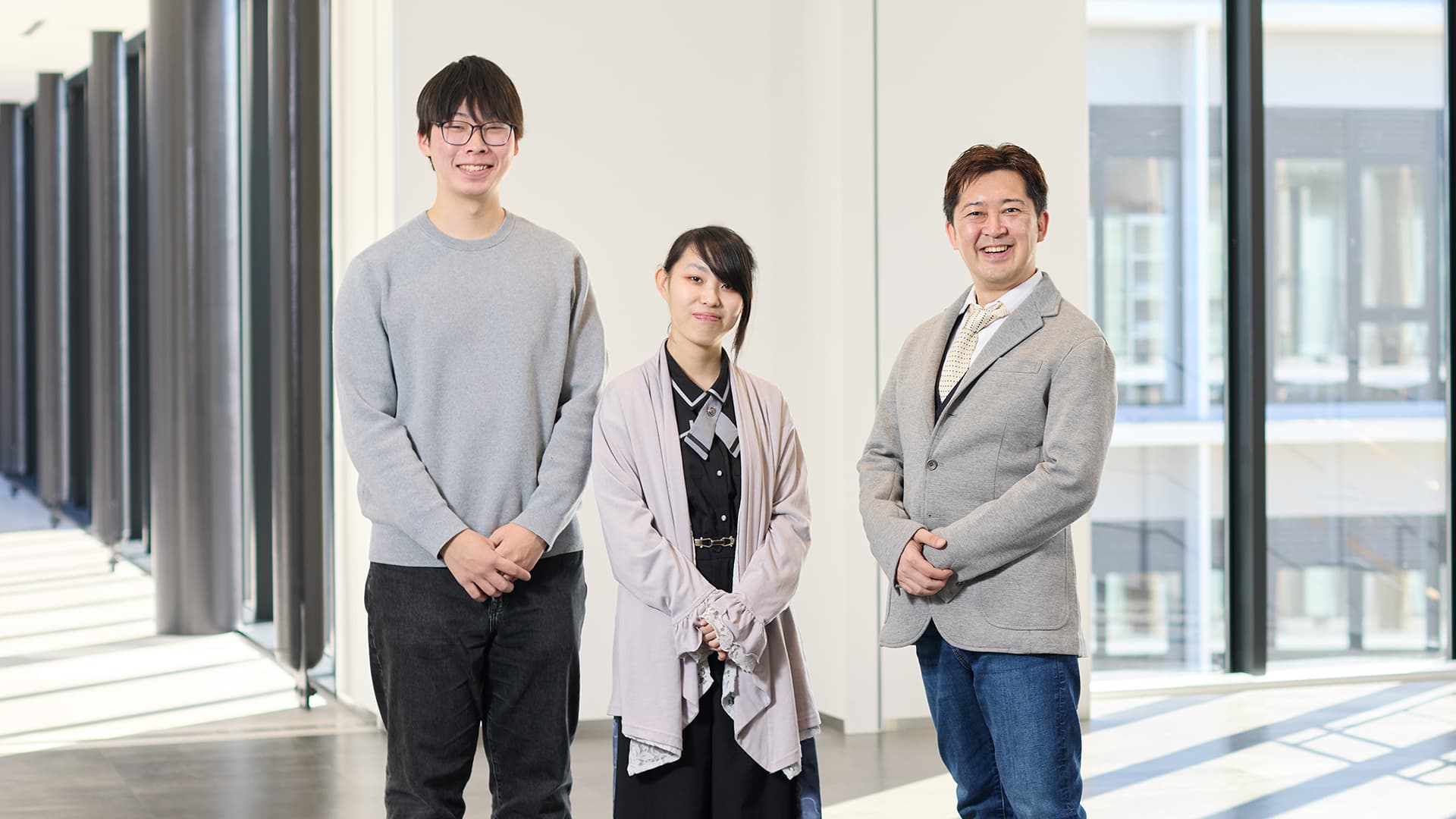
学生:想定していた答えより、かなり広義なものに聞こえます。
櫻井:そうですね。情報デザインというと、多くの人が情報技術いわゆる IT を思い浮かべるでしょう。IT をどう駆使するかということに終始するのですが、社会から要請されているものはもう少し広い意味を持ち始めています。情報そのものの意味さえ変わっているのです。昔は王様とか権力者しか情報を手に入れることができませんでした。 そうした状況では、情報を手に入れることそのものが大きな意味を持ちます。 ところが、インターネットが出てきて、私たちの生活はもう完全に変わってしまったので、目に飛び込んでほしくない情報まで脳に入 ってきてしまうっていうのが今の情報の問題点なのです。自分たちが信じて必要だと思う情報をどう捕まえて、どう処理するか、どう解釈するかという受け手側の情報が価値を持ち始めるのです。これを扱う技術は、じつはまだ体系化されてないのです。たとえば、センサーなら何をどう掴めるか、AI なら何ができるか、この情報とのやりとりの中で発生するのがじつはデザインの領域で、情報とデザインが一緒にうまくやっていくためにはその仕組みをうまく組み立てなければなりません。どうすればそれが実現できるのか。情報デザインという領域でちゃんと勉強すると、世界中で活躍できます。学生:櫻井先生は世界で活躍するブリッジ人材の重要性をどうお考えですか。
櫻井:ブリッジ人材のことを、私は「日本語と日本語の翻訳者」と呼んでいます。 企業の問題点というのは、経営者が話す言葉を従業員はまったく理解できない。研究開発部の人たちが何を喋っているのか営業には一つも通じない。デザイナーはデザイナーとしか会話ができない。こうした状況においても、情報デザインを学んだ人たちは双方の主張を融合できる力を持っているので、速やかに交通整理を行い、コミュニケーションがうまく流れる環境を生み出すことができます。ブリッジ人材と聞くと、語学堪能な人と思うかも知れませんが、語学の問題ではありません。何語であれ、その場に必要なコミ ュニケーション環境を生み出せる能力が問われているのです。

学生:私たち二人、同じチームでグローバルな課題と向き合うコンテストに参加しました。そのプレゼンテーション資料を見てもらってもいいですか。
櫻井:もちろんです。どういったテーマなんですか。
学生:まず新宿で開催された「グローバルフェスタ JAPAN2024」から。これは、国内最大級の国際協力イベントで、今回は「スマホを活用した平和へ導くアプリや WEB サービスのアイデア」が課題に挙げられました。私たちのチームは「仕事があって学校で学べない子どもたちがスマートフォンで学べる教育アプリケーションを提案し、技術的な視点からも高く評価していただきました。
櫻井:素晴らしいですね。他にもあるんですか。
学生:こちらは提案内容は今のものと変わりませんが、金沢で開催された学生ビジネスアイデアコンテスト「M-BIP」に出展したところ、入選者に選んでいただきました。「1 分間スピーチ」という企画の中で数十名の前でアイデアを発表したのですが、本番は全然ダメでしたね。
櫻井:自分の伝えたいことっていうのは、伝えられないものなんですよ。でも、その経験もいい学びですよ。今度はそうならないように工夫するようになるから。

学生:これから情報デザインの分野を目指す人に必要なものとは何ですか。
櫻井:今までの学校の学びが正解と呼んできたもの、正解の定義が大きく変わってきてるっていうのが今現在なんですね。穴埋め問題の穴を埋めて良い点を取るということより、その四角い枠をどう作るかというところに優秀さを見出すようになってきている。なぜかと言うと、AIとかロボットとか複雑に多様化していく社会の答えは誰にもわからないから。それをどう切り取るかっていう能力がすごく求められてるんですよね。ではこの 4 年間をどう使うか。研究に没頭して修士や博士を取れる大学へ行くか。2 年で手に職つけてすぐに稼げる専門学校へ行くか。私は 4 年間専門的な領域で実証しながら学ぶということができるなら、この専門職大学は結構面白いんじゃないかと思うんです。き っと、ちょっと変わった子たちが集まるでしょう。妙に頭がいいヤツとか、口ばっかりで何にもできないヤツとか、コミュニケーションが全然とれないヤツとか。結構ぐちゃぐちゃっていて、でもそれが面白いクラスターというか、コミュニティを形成していくはずです。とにかくやりながら学ぶ、学びながらやる。そういう環境を求めて 4 年間を過ごしたいんだったらぜひ専門職大学。しかも情報デザインという意味であれば、この TID という選択肢は非常に面白いと思います。