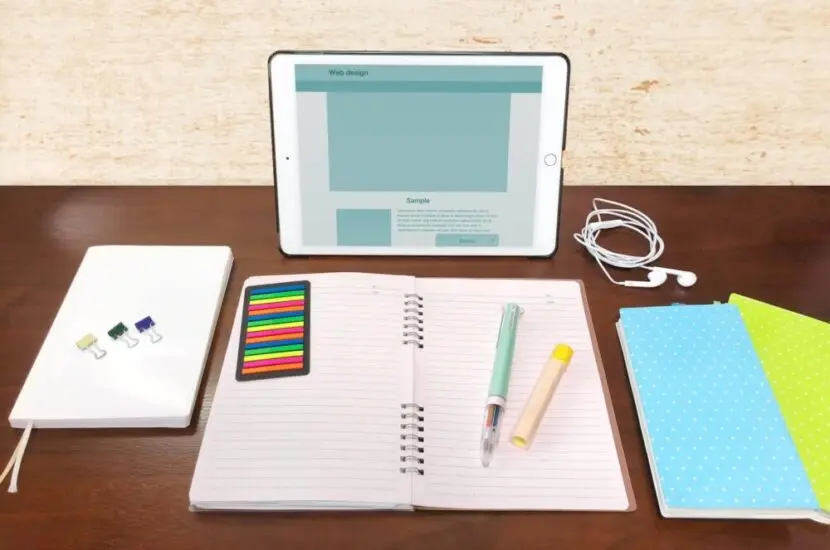仮想空間(メタバース)とは?具体例や将来性について解説
仮想空間(メタバース)は近年、注目を集めています。大企業がメタバースを意識して社名変更を行ったことも一時期話題になりました。
しかし、
「メタバースって具体的に何を指すの?」
「VRとは何が違うの?」
といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、メタバースの定義やVRとの違い、最新の活用事例、将来性、そして必要とされるスキルをわかりやすく解説します。
| TIDのオープンキャンパス・学校説明会はこちら ▶️ |
記事の概要
仮想空間(メタバース)とは

メタバースとは、アバターとして動き回れる仮想空間のことです。具体的な定義は、実は決まっていません。
メタバースという言葉は1990年代のニール・スティーヴンスンの著書『スノウ・クラッシュ』の中に登場し、Meta(超越)とuniverse(宇宙)を合わせた造語が由来です。このメタバースの由来と現在のメタバースの共通点は、私たちが直接見ている世界だけではなく、より高次元の視点で表現された世界の中に自身をアバターとして投影できることにあります。
例えば、VTuberでも使われるアバターなどはメタバースにおいてもっとも重要な要素です。また、最近では、文字や音声でコミュニケーションが取れることはもちろん、自身の動作や表情などを自身のアバターに連動させることもできるようになり、よりその人の個性を表現できるようになってきています。
さらに、コミュニケーションを取る場合は、一方的だけではなく、複数のユーザーアバターと同じ空間内で一緒にダンスするなど、様々なアクションを自由にできるようになっています。
このような特徴から、メタバースはゲーム、教育、エンターテイメント、ビジネスなど多くの分野において使用されています。
仮想空間でできることと可能性
仮想空間でできることは以下のように多くの用途があります。
- 世界中の様々な人と自然に出会える
- メタバース内のイベントで”一体感”を体験できる
- 自分好みの空間を作り、他人と共有できる
- 作成したアイテムを仮想通貨等で売買できる
などがあげられます。
最近では、仮想空間内のアバターやアイテム、街(土地)といったデジタルデータに対する権利を証明する手段として、NFT(Non-Fungible Token)が注目されています。
NFTとメタバースの違い
NFTとメタバースは混同されがちですが、大きな違いはその役割です。NFTはデジタルデータの所有権を証明する「資産」、一方メタバースはユーザーが交流できる「場所」を指します。たとえば、メタバース内でNFTを用いることで、アバターの服装や土地を希少価値のある資産として売買できるようになります。この2つは別の概念ですが、相互に補完し合う関係性にあります。
メタバースには以前からリアル通貨との換金が可能な仮想通貨を用いた経済システムが存在します。例えば、人気のゲーム内では、仮想の土地の価格が上昇するなど、魅力的な空間ほど価値が高まります。
また、アバターの見た目を変化させるための服装や髪型などのアイテムも取引の対象となります。こうした売買を異なる国のユーザーが混在するメタバース内において行うためには共通の通貨である仮想通貨が必要です。
かつてはメタバース内の仮想通貨の扱いに対する法律が整備されていませんでしたが、現在はキャッシュレス化の進展に伴い、運用ルールや税制面も整えられ、仮想通貨を用いた経済システムが構築されつつあります。
メタバースではNFTを使うことで、アバターや土地、グッズなどに希少価値を持たせて売買できるようになります。
ユーザーは、仮想通貨やNFTを用いた取引を行うことでメタバース内での活動を通して経済的な価値を生み出すことも可能となり新たなビジネスモデルも生まれています。
仮想空間 (メタバース)とVR/AR/MR/XRとの違い
メタバースには様々な解釈が存在していますが、一般的に、他の誰かと交流できる要素がないものはメタバースとは考えられていません。パソコンの性能やインターネット3Dの技術の向上により、誰もがより手軽に利用できるようになってきたため、エンジニアに限らず誰でも手軽に利用できるようになってきています。
VR
VRとは、「Virtual Reality(バーチャルリアリティ)」の略で、「仮想現実」とも呼ばれる技術のことです。ヘッドマウントディスプレイと呼ばれるゴーグル型のデバイスを用いて、デジタル上に再現された仮想空間に没入し、まるでその場にいるような体験ができます。
つまり、VRとは仮想空間に入るための「手段」であり、仮想空間は「場所」になります。VRはすでにゲームや映画、旅行などの分野でも活用されています。
AR
VRやメタバースと似た概念にARがあります。ARとは、「Augmented Reality(オーグメントリアリティ)」の略で、「拡張現実」と訳されます。現実世界と仮想空間を重ね合わせることで、現実が拡張したかのように感じさせる技術です。世界中で人気となった「ポケモンGO」もこのAR技術を用いたゲームです。
MR
MRとは「Mixed Reality(ミックスドリアリティ)」の略称で、複合現実と呼ばれます。現実空間と仮想空間を融合させた技術で、AR(拡張現実)とVR(仮想現実)の要素を組み合わせたものです。
MR専用のメガネ(MRグラス)やヘッドマウントディスプレイを使用すると、現実の空間に、バーチャルの情報が複合されて表示されます。
MRの特徴として、MRグラスを装着した複数の人が同じ情報を共有できる点が挙げられます。そのため、製造業や医療現場などでは、複数人が同じ視覚情報を共有しながら作業を進めることが可能です。
XR
XRとは「Extended Reality(エクステンテッドリアリティ)」または「Cross Reality(クロスリアリティ)」の略称で、現実空間と仮想空間を融合する技術の総称です。「X」は様々な文字が入ることを示しています。これまで説明してきたVR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)はいずれもXRに分類されます。XRはこれらの技術を包括する概念であり、さまざまな分野での活用が進んでいます。
仮想空間(メタバース)の種類と具体例
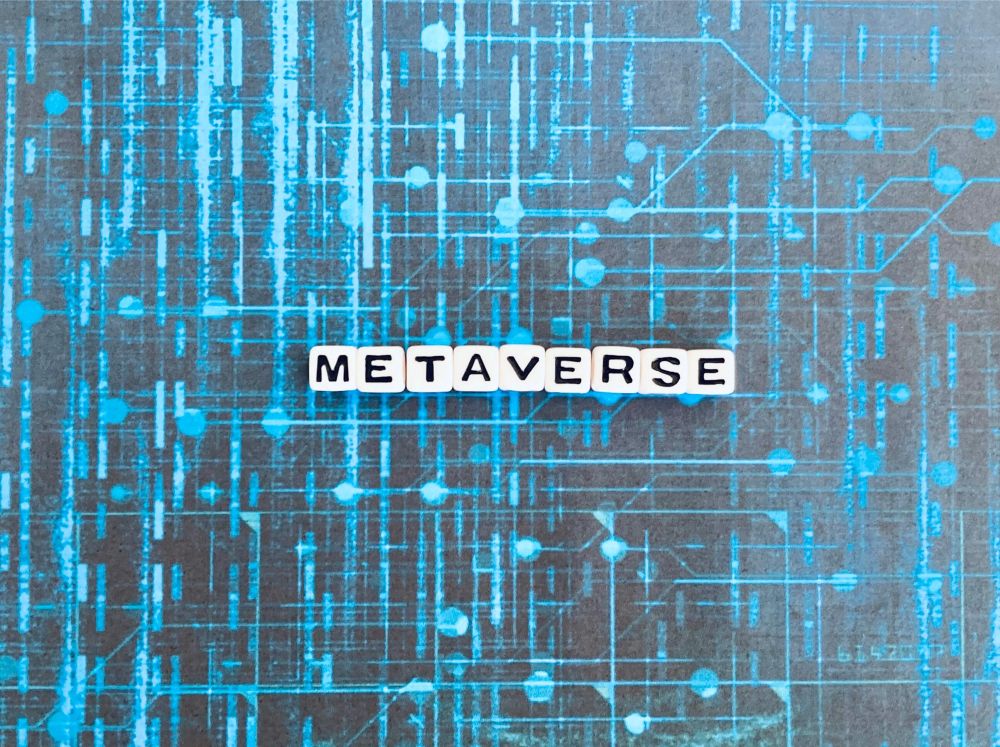
ここからはメタバースの具体例をみていきましょう。各ジャンルでどのように活用されているかを知ることで、今後の発展を予測しやすくなるでしょう。
イベント系
例: cluster(クラスター), Vket Cloud(ブイケットクラウド), VirtualCast(バーチャルキャスト), VARP(ヴァ―プ), VRChat
日本国内では、比較的早く3Dキャラクターを容易に制作できるツールが登場し、VTtuberとして自己表現する人も多く見るようになりました。技術的制約により、アバターの自由度が制限される場合が多いものの、アイドル的アバターや、芸能人アバターなどを用いたイベントが頻繁に開催されています。また最近では、企業の商品紹介や会社紹介を行う就職活動、観光案内など、エンターテイメント以外の分野でもメタバース活用が増えてきています。
ゲーム系
例: Minecraft(マインクラフト)Roblox(ロブロックス), Fortnite(フォートナイト), IMVU
ゲーム系メタバースは、イベント系メタバースの一部とも考えられますが、有名なゲームの世界観をそのままメタバースとしても体験できるコミュニケーション空間として、注目されています。お気に入りのキャラクターと同じ服装をアバターに着せて、友達のアバターと一緒に街を探索するなどの体験が家にいながら可能です。そのため、キラーコンテンツを持つ多くのゲーム会社やアニメ制作会社が注目をしています。
クリエーター系
例: Minecraft, SecondLife(OpenSim), STYLY
クリエーター系メタバースは、ユーザーが自由に好きなアイテムを制作し、好きな空間を作成して他者と共有し、楽しむことを主な目的としています。ゲームのような目的・目標が設定されていないため、利用方法はユーザー次第です。これらのメタバースは長年存在しつづけており、「元祖メタバース」として再び注目を集めています。
自治体のメタバース活用
日本国内の自治体によるメタバース活用も注目されています。東京都江戸川区は全国初の「メタバース区役所」の実証実験を開始し、庁舎に行かずに、パソコンやスマートフォンでアバターを操作し、相談や申請ができる「メタバース区役所」の実現に向けて取り組んでいます。
誰もが使いやすい「メタバース区役所」を実現するため、専門的知見や人的資源を有する東京情報デザイン専門職大学との連携を行っています。
引用:東京都江戸川区 江戸川区区役所公式HP
また、最近では、メタ社が人工知能(AI)モデル「Meta Motivo」のリリースを発表しました。このモデルはアバターにありがちな体の動きの問題を解決し、より人間らしいリアルな動きを実現することを目指しています。このように、メタバースは新しい技術との融合によってさらなる発展を遂げています。
仮想空間(メタバース)の課題と求められる人材

様々な大手企業がメタバースの可能性に大きな期待を持っている一方、技術面だけでなく、その運用面や法律面で解決すべき課題が多く残っています。その一因として、メタバースという概念に対する捉え方の違いです。
メタバースは現実世界の秩序の上に構築された単なるシステムであり、ソーシャルゲームなどと同様に、サービス内でのトラブルは現実の法律に基づいて判断されます。しかし、メタバースを現実とは独立したもう一つの「現実」として捉えている人も少なくありません。
デジタル所有権の課題
例えば、メタバース内で作成されたアバターやアイテムは、システム的にはユーザーに提供されたサービスの一部に過ぎません。そのため、サービス終了とともにこれらのデータは消失し、所有権は認められません。
しかし、長年自分の分身として利用していたユーザーにとっては、心理的になかなか受け入れにくい面があります。
海外では、メタバース内で制作されたデジタルコンテンツの取り扱いを明確化する事例も見られますが、まだ統一的な基準は存在しません。今後は、メタバース利用時にデジタル資産の権利に関するわかりやすい説明や世界共通の表示があると、さきほどのようなトラブルも少なるかもしれません。
著作権の課題
また、メタバース内では自宅のような仮想空間で友人と映画や音楽を楽しむことも可能です。現実では問題のない行為でも、仮想空間では著作権を侵害する可能性があります。例えば、映画や音楽を共有する行為が、システム的には無許可でのコンテンツアップロードとみなされることがあります。
さらに、これがライブ会場のような大きな建物のスクリーンに表示され、不特定多数のユーザーがいつでも鑑賞できるようになっていたのなら、明らかな著作権侵害とみなされても全く不思議ではありませんが、この境目はどこにあるのでしょうか?そのようなトラブルを未然に防ぎ、ユーザーが安心して楽しめるシステムを作っていくことも重要です。
ただし、例え、いかなる技術や法律が整備されたとしても、理屈だけでは納得のいかないユーザーの心理面、価値観からくるトラブルをすべて防ぐことはできず、場合によっては企業イメージを大きく損なう危険性すらあります。そのような事態とならないために、メタバースの本質をしっかりと見極め、多様性をふまえた行動ができる力を企業自身も身に着けていく必要があります。
このように、メタバースには解決しなければならない技術的な課題・法律的な課題など非常に多く存在する一方で多くの企業や自治体など様々な分野からの期待もますます高まっています。つまり、それだけメタバースには非常に多くの可能性に満ち溢れているということが言えるのです。
最後に、メタバース分野で求められる人材として重要なスキルを紹介します。
- ダイバーシティ(多様性)視点で考える力と情報デザイン力
- コミュニケーション力
- コンピュータービジョン、ネットワーク技術、AI技術など
以上からもわかるように、メタバースというものを単に目に見える側面だけではなく、その本質を含めてしっかりと捉える力は、実はメタバース分野にとどまらず幅広い業界で必要とされているものばかりなのです。
仮想空間を作り出すVRエンジニアとは

VRエンジニアとは、メタバースなどの仮想空間を作り出すためのコンテンツなどを開発する技術者のことを意味します。例えば、360°の3D仮想世界を作り出す、プラットフォームの拡張を行うなどはVRエンジニアの業務内容となります。
また、VRエンジニアもコンテンツを制作するフロントエンド開発とプログラムを作成するバックエンドに分かれる点も知っておきましょう。使用するプログラム言語は所属する企業によって異なるものの、Java Script・C#などが代表的です。
VRエンジニアの仕事内容
VRエンジニアの仕事内容は、コンテンツ設計から制作、デバッグまで含まれます。例えば VRアプリやゲームで表示するフィールドからキャラクターだけでなく、場合によってはサウンドやストーリーまで検討しなければなりません。
また、設計した後にはゲームエンジンを用いて実際のコンテンツ作成に入っていきます。グラフィック・シミュレーションなどの細かい要件もチェックする必要があります。担当する案件によっては、CGだけでなくリアルの映像などと組み合わせることもあるため、スキルの高さを要求されるケースも少なくありません。
VRエンジニアの魅力
VRエンジニアの魅力は以下になります。
- 未経験から挑戦できる
- スキル次第で年収に期待できる
- 市場が拡大傾向にある
エンジニアの中でもとくに初心者から挑戦できる職種である点が魅力の1つといえます。その理由は、VRそのものがまだ発展途上の市場であるためです。市場と共にスキルを伸ばしていくことで高収入を目指すこともできます。
また、VRエンジニアを欲する企業は今後増加していくと想定されます。メタバースに関連するコンテンツであればVRの技術が必須となるだけでなく、大企業も参画していることから今後は中小企業にもその動きが波及していくでしょう。
加えて、前項でもふれましたが市場そのものが拡大傾向にあるため、仕事に困ることはありません。企業の評判や規模、業界などはよく調べる必要があるものの、スキルを磨くという意味では選べる選択肢が広い点は魅力の1つだといえます。
VRエンジニアに必要なスキル
VRエンジニアに必要なスキルは以下になります。
- Unityなどのゲーム開発用ソフトウェアが操作できる
- JavaScriptなどのプログラム言語を使用できる
- コミュニケーション
- 情報収集
- 探求心
VRエンジニアの業務範囲は、市場の拡大と共により広がっていく可能性があります。そのため、アバターやプラットフォームに必要とされる技術的なスキルとコミュニケーション能力の他、情報収集能力も試されることになるでしょう。
また、大規模なプラットフォームに関わる場合、多くの人の意見を聞いて端的にまとめて人に伝えるといったスキルも大事です。
仮想空間(メタバース)を学ぶなら東京情報デザイン専門職大学

メタバースは今後伸びしろのある市場の1つです。VRエンジニアにとって活躍の場があるというだけでなく、今後はあらゆる産業の企業が参画する可能性もあります。また、市場の需要に対して、人材の供給が間に合っていないことから、今後も多くの企業からVRエンジニアは求められる業種だといえるでしょう。
そして、VRエンジニアは未経験者でも就職できる可能性のある業種でもあります。しかし、必要なスキルとしてプログラム言語だけでなく、ゲーム開発用ソフトウェアも含むことから「学生時代から専門的にVRを学び、将来的にVRエンジニアとして働きたい」という方もいるのではないでしょうか。
その場合は、選択肢の1つとして東京情報デザイン専門職大学を検討してみてください。本学は、専門的な知識だけでなく、社会に出てすぐに活躍するための技術や思考力をあわせて身に付けることができる新しい制度の学校です。
また、VRを専門的に学びたい場合には、2年から4年次に行う長期インターンシップの中で、より最先端技術や仕事に対する意識にふれることが可能です。
IT・AI・ゲーム業界に興味のある方へ!
東京情報デザイン専門職大学ではオープンキャンパス・学校説明会を開催しています!

オープンキャンパス・学校説明会
情報デザインを使う企業・業界から講師が来校。興味のある分野を選び「情報デザイン」の一歩を体験してみよう。