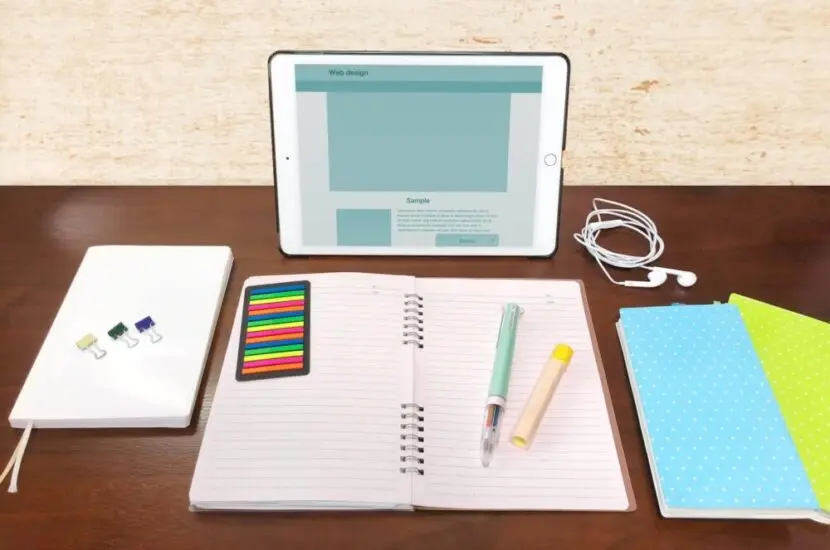クラウドエンジニアになるには? 仕事内容から必要な資格、年収について解説

クラウドサービスの市場規模は右肩上がりで拡大し続けており、特に電子データの保管・共有手段として多くの企業に利用されています。また、社内に保守・運用体制を持つ必要がなく、契約してあればどこからでもアクセスできる利便性が評価されています。
そのため、今後もクラウドサービスとクラウドサービスの開発から運用まで行うクラウドエンジニアのニーズは、高まっていくと想定されるでしょう。しかし、クラウドエンジニアになる方法やクラウドサービスが、どういったものかわからないというケースも考えられます。
本記事では、クラウドサービスの概要にふれたうえでクラウドエンジニアの仕事内容や将来性、なり方について詳しくみていきましょう。
| TIDのオープンキャンパス・学校説明会はこちら ▶️ |
記事の概要
クラウドとは
クラウドとは「雲」であり、情報システムが身近な地上ではなく、どこかよくわからないところに設置されていて、場合によっては知らない間に移動していることを意味しています。また、私たちが欲しいのは、情報システムが提供するサービスであって、コンピュータやネットワーク装置などのハードウェアではないということも意味しています。
1990年頃から、企業等の組織内に複数のサーバーコンピュータを導入し、Email、ファイル、データベース、資産管理などの社内向けサービスを提供していました。しかし、最新の技術に合わせてシステムをアップデート、拡張し、新たに生じるセキュリティの脅威に対抗する管理コストが膨らむばかりでした。
このような情報システムを運用している企業は、自社が必要とする計算負荷と通信容量は大きく変動しているが、大きめの負荷に合わせてシステムを構築しておけば、自社の需要は十分にまかなえる一方、負荷が下がった時には、このシステムの余力を他の企業に提供できることに気がつきました。
情報システムは、そのユーザーから距離的に離れた環境に置かれますが、2000年以降急速に発展してきたインターネット技術を活用すれば、リモート環境のサーバーであっても近くのサーバーと遜色ないサービスが受けられます。それどころか、この情報システムは、自社の中に設置する必要がありません。むしろ、電気料金が安く、寒冷な気候の土地に置いてネットワーク接続すれば、より効率的な運用ができるのです。
このような考えに基づいて構築される遠隔・分散型の情報システムが、クラウドです。
クラウドサービスとは
クラウドサービスは、大きく分けて次の3種類に分けられます。
- SaaS(サース)・・・Dropbox、Salesforceなど
- PaaS(パース)・・・Google App Engineなど
- IaaS(イアース)・・・Amazon Elastic Compute Cloudなど
クラウドが提供するサービスは、実現したいアプリケーションとの関係に応じて、SaaS, PaaS, IaaS などの区別があります。いずれも、aaS の部分は、as a service の略であり、冒頭のS, P, Iは、それぞれSoftware, Platform, Infrastructure を指します。いずれも、さまざまなレベルの機能を「サービス」として提供することを強調しています。
SaaS (Software as a Service) は、PCにインストールして使っているさまざまなソフトウェアをクラウドで提供する形態です。たとえば、PCでは、MS Word、 Power Point などのソフトウェアを使うことが多いのですが、Google Workspace や Microsoft Teams などのクラウドサービスは、これらのオフィスソフトとほぼ同じ機能を遠隔のクラウドサーバーが提供します。ただし、それを利用するためには、PCには必ずWebブラウザが必要です。すなわち、SaaSの機能は、Webサービスとして提供されます。
PaaS(Platform as a Service) は、必要なミドルウェアを選択して利用します。ユーザーは、ミドルウェアをインストールする手間が省けるだけでなく、ミドルウェアに最適な設定で利用を開始することができます。
IaaS(Infrastructure as a Service)は、ハードウェアだけ(bare metal)、あるいはOSと基本的なシステムソフトウェアだけを搭載した状態でサービスします。利用には手間がかかりますが、自由度の大きいシステム構築ができます。
クラウドサービスを利用した場合、経年劣化によるハードウェアの交換、ハードウェアを稼働させるための電気代や保管するための設備などが不要になるため、ランニングコストを削減することが可能です。
インフラエンジニアが対応するサービスとしては、PaaSやIaaSの開発から運用・保守までを担うケースが一般的に多いです。
クラウドエンジニアとは

クラウドエンジニアとは、このようなクラウドを構築し、情報サービスを実現していくエンジニアです。より細かくは、クラウドサービスを提供する側のインフラエンジニアと、クラウドの上でサービスを利用する側のクラウドエンジニアがいます。
クラウドサービスを提供する代表的な企業は、Amazon AWS、Google GCP、Microsoft Azure ですが、これらの企業の中でクラウドサーバーの設計、構築、運用に関わるのがインフラエンジニアです。ここでの重要な技術は、仮想化と高信頼化技術です。
仮想化とは、1台のコンピュータを複数のコンピュータに見せる技術(VM: Virtual Machine)です。またネットワークを仮想化するSDN (Software Defined Network) も使われます。
クラウドは、社内のサーバー以上の高信頼性サービスの提供を目的にしており、システムの多重化や監視によりデータベース等の高信頼化を図り、顧客の大切なデータを守ります。また、変動する需要に合わせてサービスを提供するためのロードバランシングやスケール化技術も高信頼化に重要です。
これらのサービスのユーザーとして、Web、データベース、AIなどのアプリケーションを実現したり、社内の情報サービスのクラウド化を図るのがクラウドエンジニアです。クラウド上のアプリケーションは、さまざまなソフトウェアを組み合わせて構成されるので、クラウドエンジニアには、各種のプログラミング言語を使いこなす能力が求められます。特に必要なのは、C, C++などのシステム記述言語、bash、 perl などのスクリプト言語、またJavascript、 Python、 SQL などのアプリケーション記述言語です。また、クラウドのユーザーアカウントやネットワークのファイアウォールを適切に管理・設定してセキュリティを高めるのもクラウドエンジニアの重要な役割です。
クラウドエンジニアの年収

求人ボックスによると、クラウドエンジニアの年収600万程度で年収は比較的高めだといえます。
引用:クラウドエンジニアの仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)
インフラエンジニアと同様の知識が必要となるだけでなく、クラウドサービスに対する深い理解も大切な要素です。
市場規模が拡大傾向にあるため、経験やスキルによって年収を高めていきやすいと想定されます。また、クラウドサービスそのものに知見があるエンジニアが求められているため、ニーズに合わせることができれば、予想以上の年収を提示されるケースもあるといえるでしょう。
クラウドエンジニアの仕事内容

クラウドエンジニアは、クラウドサービスを利用してネットワーク、サーバーを構築し、クラウドの最適化を図るために保守・運用を行うのが主な仕事です。他のインフラエンジニアと異なり、従来発生していたサーバーのラッキングや配線、経年劣化による交換など、物理的な作業を行う必要がないため、人的作業による負担を大幅に軽減できます。
では、クラウドエンジニアの仕事内容を細かくみていきましょう。
クラウドエンジニアの仕事は、情報システムを設計・開発・運用する仕事であり、いわゆる情報システムエンジニアと大きく変わることはありませんが、その活躍の舞台がクラウドであることが大きな特徴です。
サービスの創造
情報デザイン的に考えると、クラウドを用いるというのは、価値の創造の一つの方法に過ぎません。最も大切なことは、新しいビジネス、新しい生活体験、新しいコミュニケーションなど、関係する事業領域の中でどのような新しい価値を実現していくべきかをデザインすることです。この価値をITを用いて実現する方法を検討します。そのような情報が生み出す価値をここではサービスと呼びます。
サービスの設計
デザインの方向性が決まると、その実現にはクラウドが適しているのかを検討します。実際は、スマートフォンやウェアラブルデバイスと連携させたり、既存のデータベース等と組み合わせることを考えるでしょう。たとえば、スマートフォンを使うことにすると、そのモバイルアプリケーションを開発するエンジニアと連携して、スマートフォンが収集するデータをクラウドに集積することを検討すべきです。
クラウドで実現することを決めたら、次は、実現したいサービスにとって最適なクラウドの形態はSaaS、PaaS、IaaSのどれが適当か、その開発や運用のコストを見積もりながら検討します。
クラウドの形態が決まったら、どういうソフトウェアを導入するか、他のシステムとどのような連携(通信)を行うか、どのようなデータを蓄積・活用するか、またユーザーのアクセス経路や個人情報などの機微情報のありかなどを設計します。この設計フェーズでは、開発が終わった後に行う各機能のテストの方法も併せて設計します。このような設計は、SysMLやUMLなどの標準にしたがって図を描き、仕様書として文書化します。
サービスの構築
設計フェーズで作成した仕様書やUML図にしたがって、システムを開発します。必要ならば、適切なプログラム言語を選択して、新たなソフトウェアを作成します。
コンポーネントが複数ある場合、担当を分けて並行して開発を進めます。担当者は、与えられたコンポーネントの開発に集中しますが、チーム間でコミュニケーションを取り、必要に応じて担当者が交代するなどして、全体の連携をとります。また、コンポーネント開発の負荷を平準化して、すべてのコンポーネントがほぼ同時に完成することを目標にします。
コンポーネントができたら設計時に作成したテスト法に従って機能が正常か、負荷に耐えられるか、セキュリティが保護されているかなどをテストします。さらに、コンポーネントの組み合わせについても同様のテストを行います。
サービスの展開
社内のテストで完動することが確認できたら、関係者に公開して、システムのテスト運用を開始します。この時点では、いつでもシステムを停止して改良作業が行える体制を維持しておきます。セキュリティが心配な場合は、実際に攻撃を試みるペネトレーションテストを実施します。安全に信頼性良いサービスが展開できるとわかったら、いよいよ一般にサービスを公開します。
サービスの運用・保守
安定に稼働するシステムにもさまざまなメインテナンスが必要です。たとえば、使用しているソフトウェアコンポーネントのセキュリティアップデートを行う必要があります。ユーザーアカウントの追加や、システムの拡張も起こります。システムに改変を加えた場合、担当者が交代しても状況が把握できるよう、もともとの仕様書や設計図面を適切にアップデートすることが重要です。
運用が長期に及ぶと、コンピュータの処理性能やストレージ容量が不足することがあります。ベースとなるオペレーティングシステムやコンピュータハードウェアが老朽化することもあるでしょう。しかし、クラウドでは、OS以下は仮想化されているので、コンピュータを取り替えたり、ストレージを追加することが比較的容易です。
クラウドエンジニアに必要なスキル・能力

クラウドサービスの需要の高まりにともない、オンプレミスからクラウドへ移行する案件も増加傾向です。コミュニケーション能力を活かし、クライアントに仕様を伝え、オンプレミス環境で、動作している現行システムの開発者へ的確にヒアリングを行うこともあるといえるでしょう。
また、クライアントに対し企画を提案する機会もあるため、クライアントの求める要件を満たす企画を作成するスキルが必要とされます。クライアントにわかりやすくプレゼンテーションを行う能力も重要です。
そして、開発に参加する際にはディレクションやマネジメントを行うスキルも必要です。たとえば、納期に間に合うようにスケジュール管理を綿密に行ったり、チームの進捗を見て軽微な調整を行ったり、状況に応じて冷静に対応する能力が求められます。
セキュリティ、ミドルウェアに対する知識
ミドルウェアに対する知識・スキルも大切です。ミドルウェアとは、OSとアプリケーション間で複雑な処理を行うシステムです。たとえば、Webサイトへのアクセスがあったときにそれを画面に表示させるWebサーバー、データを格納するデータベースなどがミドルウェアに該当します。
システムをクラウド化する際、これまでどおりオンプレミス環境で開発を行う箇所と、クラウド化する部分を切り分けることがあるため、ミドルウェアの知識・スキルが身についていれば開発で役立つことも増えるでしょう。
プログラミングのスキル
クラウドエンジニアは必須ではないものの、プログラムの知識・スキルがあると開発の幅が広がりメリットがあるといえます。プログラミング言語を習得すれば、システムを自身でコーディングし、作業の自動化も可能です。
一度作業を自動化すれば、次に似たような開発を行う際にコードを流用できるため、作業効率のアップが望めるでしょう。
サーバー・ネットワークの知識
クラウドエンジニアには、サーバー・ネットワークの知識が必要です。業務として、ITインフラのクラウド化、クラウドの構築などを行わなければならないためです。
また、サーバー、ネットワークのオンプレミス環境に関する知識があれば、クラウドだけでなくサーバーエンジニアやネットワークエンジニアへのキャリアチェンジも見込めます。
クラウドエンジニアに役立つ資格

クラウドエンジニアで資格を求められるケースはないものの、スキルを保有していることを示すために役立つといえます。実務に知識が役立つ面もあるため、取得を目指してみましょう。
AWS認定資格
AWS認定資格とは、Amazonが提供するAWSを利用したクラウドの設計・運用のスキル、知識を証明することのできる資格です。AWSはクラウドサービスのなかでも市場シェアの高いサービスです。
AWS認定資格は基礎コース・アソシエイト・プロフェッショナルの3つのレベルがあり、専門的な分野ごとに分かれています。全合計で11個の資格があるため、自身のスキル・経験に合った資格を取得しましょう。
AWS公式サイト「AWS認定」
Google Cloud 認定資格
GoogleCloud認定資格とは、GCPを使用したクラウドの設計・運用のスキル、知識を証明できる資格です。基礎レベル、Associate、Professional、Expertの4つのレベルに分類されています。出題範囲は、サービス概要からデータ分析など専門的な内容まで分かれているため、受験する資格内容はよく確認する必要があります。
GoogleCloud公式サイト「GoogleCloud認定資格」
CCSP認定試験
International Information System Security Certification Consortium(ISC)²が実施している、クラウドのセキュリティに関する資格です。受験対象者はIT勤務歴5年以上、うち情報セキュリティに関する業務が3年以上とされており、非常に高度な内容が出題されます。
試験内容に関しては、クラウドの概念やコンプライアンスなどもふくめて1000点満点中700点以上を取得する必要があります。
CCSP公式サイト「認定要件」
CompTIA Cloud+認定資格
CompTIA(the Computing Technology Industry Association)が認定している、クラウドの設計・運用のスキルを証明できる資格です。クラウドの設計・構築の基本知識からセキュリティ、構築後の管理方法、トラブルが起きた際の対応についてなど幅広い範囲から出題されます。
CompTIA公式サイト「CompTIA Cloud+」
Linux技術者認定資格(LinuC)
Linuxに関する知識やスキルを証明することのできる資格です。Linuxはクラウド上で構築するケースが多いため、Linuxの知識は役に立つ場面が多いでしょう。レベルは3段階あり、オンプレミス環境だけでなくクラウドにも対応している資格なので汎用性が高く、おすすめの資格です。
LinuC LPI-JAPAN「https://linuc.org/LinuCとは」
クラウドエンジニアのやりがい

ここからはクラウドエンジニアのやりがいについてみていきましょう。チーム単位で一つのシステムを作り上げる達成感や、幅広いスキルを身につけられる点もやりがいにつながります。
スキルのニーズが高い
近年オンプレミスからクラウドへの移行が進んでおり、令和2年には6割以上の企業がクラウドサービスを事業に利用していると総務省が発表しています。それにともない、クラウドエンジニアの需要も高まっており、スキルを必要とする企業も多いといえるでしょう。
専門的なスキルを高め続けられる
クラウドサービス市場が拡大傾向にあることから、常に最新技術にふれたうえで、業務に活かしていく必要があります。たとえば、大きな仕様変更などは最新のシステムやサービスの内容を理解したうえで、顧客のニーズを反映したクラウドサービスを作り上げなければなりません。
そのため、知識を高めるだけでなく、スキルも比例して向上していくことが想定されます。仮に、最新技術の仕組みを把握できたうえで、高いスキルがあれば、就職や転職がしやすくなるというメリットもあります。
クラウドエンジニアになるには

クラウドエンジニアの業務では、インフラの知識が重要となってくるため、未経験の人がクラウドエンジニアになるのは簡単ではありません。エンジニア経験がない場合は、学習コストが非常に高くなると予想されるため、前述した資格を取得なども検討しましょう。
では、具体的にクラウドエンジニアになるための進路についてみていきます。
大学や専門学校で学ぶ
大学や専門学校ではエンジニアになるためのカリキュラムが組まれ、学びやすいです。時間と費用がかかってしまいますが、専門の講師が必要な知識・スキルを教えてくれ、さらに学校によっては就活の支援やアドバイスをくれるところもあるため、大学や専門学校での学習もおすすめです。
オンラインスクール
オンラインスクールは専門学校よりもコストが抑えられ、無理ないペースで学習できます。オンラインスクールの講師は、エンジニア経験のある担当者も多いためおすすめです。
インフラエンジニア
クラウドエンジニアはインフラエンジニアの知識と近いものも多いため、インフラエンジニアからクラウドエンジニアになることは難しくありません。物理的なハードウェアにふれるケースもあり、IT基盤を構築するといった役割から、クラウドサービス構築業務のみを担当するようになるといった変化があります。
仮にネットワークなどの領域を扱う場合は、キャリアチェンジも容易に行えるといえるでしょう。
クラウドエンジニアのキャリアパス

ここからはクラウドエンジニアのキャリアパスについてみていきます。クラウドエンジニアとしてスキルや専門性を高めていくだけでなく、プロジェクト全体をマネジメントする役割を担うことも可能です。
スペシャリスト
クラウドエンジニアとしての知識・スキルや最新のクラウド・インフラに関する知識を深く磨き上げ、スペシャリストとなる道があります。プロジェクトの成否に関わる業務のため、やりがいを感じながら第一線で活躍できるでしょう。
プロジェクトマネージャー
プロジェクトを管理するプロジェクトマネージャーになることも可能です。チームで仕事を進めたうえで、まとめる重要な役割で、クラウドエンジニアの経験を生かしてプロジェクトを牽引することが求められます。プロジェクトマネージャーの仕事は、プロジェクト全体を把握して、問題や課題点を的確に見つけて解決し、進捗を見ながら人員を割り当てるといった業務内容です。
そのため、マネジメントスキルをしっかり磨かなくてはなりません。円滑に開発を進めるリーダー的役割としてチームに欠かせない存在となるでしょう。
クラウドコンサルタント
クライアントに対してクラウドを活用した企画を提案する、クラウド全体の企画に関わる職種です。クラウドエンジニアとしてのキャリアを生かし、クライアントに企画を提案・クラウドサービスの導入をサポートし、クライアントに寄り添う姿勢が大切です。
クラウドエンジニアよりもさらにクライアントに近い業務となっているため、顧客折衝経験を身に着けていく必要があります。
クラウドエンジニアの将来性

クラウドサービスを活用する企業は年々増加傾向にあるため、クラウドエンジニアの需要も高まっていくと想定されます。そのため、今後も求められ続ける職種であると推測できます。また、多くの企業で導入されていることから、ネットワークに知見のあるエンジニアとして活躍することが可能です。
加えて、企業のサービスとしてクラウドサービスの機能性を前提として、自社サービスを作るといった動きも加速しているため、クラウドエンジニアの将来性は高いと想定されます。
クラウドエンジニアを目指すなら東京情報デザイン専門職大学

クラウドエンジニアは、クラウドサービスの構築から運用を行う職種です。そのため、ネットワークやプログラミング、最新のクラウドサービスの内容など幅広い知識とスキルが必要となります。
東京情報デザイン専門職大学では、3・4年次に合計600時間にも及ぶインターンシップを行うため、クラウドエンジニアに関する専門的なスキル・知識を学ぶことが可能です。クラウドエンジニアを目指す際の進路の1つとして、検討してみましょう。
IT・AI・ゲーム業界に興味のある方へ!
東京情報デザイン専門職大学ではオープンキャンパス・学校説明会を開催しています!

オープンキャンパス・学校説明会
情報デザインを使う企業・業界から講師が来校。興味のある分野を選び「情報デザイン」の一歩を体験してみよう。